トレーニングのための筋線維タイプとエネルギー貯蔵経路
記事の医療専門家
最後に見直したもの: 08.07.2025
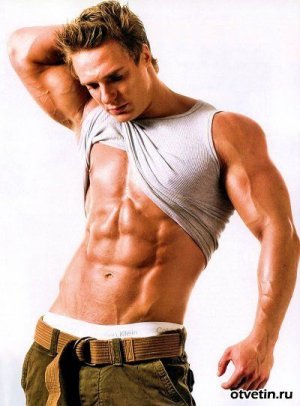 ">
">筋線維にはいくつかの種類があります。I型筋線維、すなわち遅筋線維は、収縮速度が比較的遅いです。主に好気性代謝経路を利用し、好気性エネルギー産生経路に必要な酵素(例えば、クエン酸回路と電子伝達系に必要な酵素)を豊富に含むミトコンドリアを多数含みます。また、毛細血管密度が高く、酸素とエネルギー基質を供給し、乳酸などの老廃物を除去します。
タイプ I の筋線維が多い運動選手は血中乳酸閾値が高くなります。これは、ピルビン酸をより速くクレブス回路に放出でき、乳酸に変換されるピルビン酸が少なくなるためです。そのため、パフォーマンスが長く、疲労するまでの時間が長くなります。
タイプII筋線維、すなわち速筋線維は、比較的速い収縮速度と、無酸素状態で素早くエネルギーを産生する能力を有します。タイプII筋線維はいくつかのカテゴリーに分けられ、そのうち2つは明確に定義されています。タイプII筋線維は収縮速度が高く、有酸素性および無酸素性のエネルギー産生システムがかなり発達しています。タイプII筋線維は最も速く、最も解糖作用が強いです。ほとんどの活動では、比較的ゆっくりとした筋収縮と、時折起こる短いバースト的な急速な筋収縮が可能な速筋線維と遅筋線維の組み合わせが必要です。
短距離走や激しいウォーキングなど、より多くのタイプII線維を必要とする負荷は、蓄積された炭水化物貯蔵に大きく依存します。これらの負荷は、グリコーゲン貯蔵のより急速な枯渇を伴います。遅筋線維と速筋線維の比率は、主に遺伝的素因に依存します。ヒトでは、平均して筋線維の45~55%が遅筋線維です。しかし、トレーニングセッションは筋線維の種類の分布に影響を与える可能性があります。主に有酸素性エネルギー供給を必要とするスポーツ(長距離走)に従事するアスリートでは、遅筋線維が動作筋の90~95%を占めています。
食物の化学結合のエネルギーは、脂肪や炭水化物、そして少量ではあるがタンパク質の形で蓄えられます。このエネルギーはATPへと変換され、ATPはそれを必要とする細胞構造や化合物に直接伝達します。
ATPエネルギー伝達には、ホスファゲン系、嫌気性解糖系、好気性系の3つの異なるシステムが用いられます。ホスファゲン系はエネルギー伝達速度が速いものの、その能力は非常に限られています。嫌気性解糖系も比較的速くエネルギーを伝達しますが、この経路の産物は細胞のpHを低下させ、細胞の成長を制限します。好気性系はエネルギー伝達速度が遅いものの、炭水化物や脂肪をエネルギー基質として利用できるため、生産性が最も高くなります。これらのシステムはすべて、体内の異なる細胞で同時に利用することができ、細胞環境とエネルギー需要に応じて、最適なエネルギー伝達システムが決定されます。
- 酸素とエネルギー基質の利用可能性
- 細胞環境における2つの重要な要素。
筋線維の種類とその固有の特性は、筋細胞のエネルギー伝達システムを決定する重要な要素です。食事療法や運動トレーニングは細胞環境を変化させ、エネルギー伝達システムのパフォーマンスとエネルギー基質の蓄えに大きな影響を与えます。


